イボはどうしてできる?原因や種類の違いは?おすすめの治療方法

顔や身体にできる「イボ」は、一度できると気になってしまいコンプレックスに感じてしまう人もいるでしょう。
イボは自然治癒しにくいため、どうしても気になってしまうのであれば切除を検討することをおすすめします。
イボの種類ごとに違う対処法など、気をつけたいポイントについて解説していきましょう。

記事監修者
新宿美容外科クリニック 形成外科医
井上 淳
日本形成外科学会の形成外科専門医としてあらゆる形成美容外科領域での基礎をもとに、25年にわたって多くの美容外科、整形の症例を経験。外科医としての豊富な知識や技術力からスタッフの信頼も厚く、また落ち着きのある性格や優しい対応も人気のドクター。スタッフや患者さまからは、脂肪吸引の匠と呼ばれて、親しまれている。
気軽に受けていただける処置から、高度で複雑な手術まで、患者様に満足していただける最も適した「理想のボディライン、理想のフェイスライン」の追求をしている。カウンセリングは、優しい、初めてでもいろいろと丁寧に教えてくれる、と定評があり、患者様一人ひとりの様々な悩みに正面から向き合っている。
経歴
| 1992年 | 千葉大学医学部卒業 千葉大学形成外科入局 以後、千葉大学および昭和大学の 関連形成外科勤務 |
| 2006年 | 都内美容外科クリニック 院長就任 |
| 2007~2013年 | 都内美容外科クリニック 総院長就任 |
| 2014年 | 新宿美容外科クリニック 総院長就任 |
顔や身体にできるイボってどんなもの?
イボとは、顔や身体などお肌の表面にできるできもののことです。
大きさや原因はそれぞれに違いますが、お肌の表面が盛り上がっている点が共通しています。
イボはウイルス性のもののほか、紫外線や加齢の影響によってできる場合があります。
イボは種類により形や症状が違うのはもちろん、適切な対処法も変わっていきます。
そのため「このイボが気になる」「治したい」と感じているのであれば、イボの種類を正確に見極めなければいけません。
イボの種類と主な原因とは?
イボの種類の中でも、特に多いのがウイルス性のイボです。
その中でも多いのが「尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)」と呼ばれるものです。
ヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスの2型であり、イボそのものは小さく、痛みも感じにくいのが特徴です。
ウイルスは小さな傷口から入り込んで、指などにイボを作ります。
ウイルスが体内に入り込んだときすぐイボになるのではありません。
だいたいのケースで、3~6ヵ月経ってから発生することも特徴と言えるでしょう。
治療の際には「凍結療法」と呼ばれる方法を用いることが多いようです。
治療方法については、のちほど細かく解説していきます。
続いて「伝染性軟属腫」、いわゆる水イボと呼ばれるイボも、多くの人が悩まされやすい症状と言えるでしょう。
伝染性軟属腫の特徴として、ピンクや白色をしていて、ぷっくりとしたドーム状になっていることが挙げられます。
こちらも基本的には痛みやかゆみがないため、気付きにくくいつのまにかできてしまうことがあるので注意してください。
また、伝染性の言葉の通り感染力が高いことも特徴です。
伝染性軟属腫ができた状態でお風呂やプールを使用すると、知らず知らずのうちに人へ移ってしまうことがあります。
続いて、ドーム状でなく平たいイボの場合は「青年扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)」の可能性があります。
青年扁平疣贅は、平らな形状が特徴的なイボです。
ほかのイボに比べてわかりにくく、シミと間違われることもあるため、できていても気づかない可能性がある点に注意しましょう。
自己判断が難しい場合、必ず医師に相談してください。
イボをの予防や悪化防止として意識すること
感染性のイボの場合、ほかの人へ移さないよう心がけることが肝心です。
前述のようにお風呂やプールはなるべく避けるようにしましょう。
例えば同じタオルやマット、スリッパなどを使うことでもイボが移ってしまう可能性があります。
イボができたときには、共有のものを使用することを避けるようにしてください。
また、一度イボが気になり出してしまうと「四六時中どうしても気になってしまう」と感じることがあるかもしれません。
イボはぷっくりと突出していることから、爪先でいじりながら無意識に取ろうとしてしまうこともあるでしょう。
しかし、イボを自分で取る行為は厳禁です。
自力で取ろうとしたり、削ったりするとイボが悪化し、さらに気になる状態になってしまうこともあります。
また、むやみに触ることでも悪化につながるでしょう。
必ず医師による診断の上で適切な処置しましょう。
イボの治療方法とは?
イボの治療では、冷凍凝固法という方法が用いられることがあります。
冷凍凝固法とは、その名の通りイボを急激に冷やすことで除去する方法です。
マイナス196℃という低温でイボだけを落とします。
ウイルス性のイボや老人性イボを除去するにあたって使用されることが多いようです。
この治療は一度の施術で終わるものではなく、数回の施術が必要です。
凍結のあとには、稀に痛みや水ぶくれが起きることもあります。
続いて、ラジオ波メスと呼ばれる方法もあります。
こちらの方法ではイボを焼くことによって切除します。
脂漏性角化症などの治療で用いられ、比較的傷が残りにくい方法と言えるでしょう。
出血も少なく済みますが、その後2週間ほど患部をテープで保護することになります。
ちなみに、妊娠中、授乳中の方や過度に日焼けしている方は治療そのものが受けられない可能性もあります。
必ず医師に相談し、適切な判断のもと治療を検討しましょう。
まとめ
お肌にできるイボは、種類や大きさによっては目立ちやすくコンプレックスに感じてしまう人もいるでしょう。
同じように見えても種類の異なるイボは原因や治療法も違い、中には入浴やタオルの使用を通じて感染するものもあります。
自己判断せず、必ず医師に相談して適切な判断をしましょう。
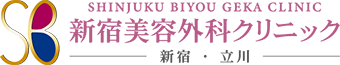


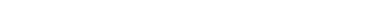 Copyright © 新宿美容外科クリニック All rights reserved.
Copyright © 新宿美容外科クリニック All rights reserved.


